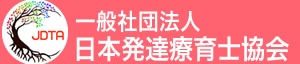当協会代表が取材を受けた「発達療育士協会を設立したきっかけ」。参考になればと思い掲載します。
ザ・ターニングポイント(エンジュリオンブック)より引用
難しい保護者対応に学ぶ
(前略)最初は(地元の小学校で)1年生の担任となった奥田幹子さん。その児童の中に見た目はまったく普通だが、学習となると少しついていきにくい、現在で言ういわゆるLD(学習障害)の子どもがいた。
ちょうど養護学級から、特別支援学級に教育現場が変わっていく時期だった。学習障害などを持った児童の親は、どうしてもまだまだ旧態の養護学級のイメージが強く、肢体障害や高次脳機能障害やダウン症の子たちと我が子は違う、と理解を得るにはハードルが高かった。
なので、担任の教諭は通常の学級の中で障害をもつ子どもについてしっかりと理解をし、勉強を教えていくことが必要だったのだ。ひらがなが書けないその子に、どうすれば勉強を楽しいと思ってもらえるか、という試行錯誤を繰り返した。
そこでわかったことが、三角形が書けたらひらがなを書けるようになるということだった。まずは線をつなぐ宿題を出して、少しずつ慣らしていく。そうすることでひらがなを書けるようになるのだった。
障害児を特別扱いするのではなく、それぞれの子に必要な対応をしているということを貫くと、その姿勢は自然と子どもたちに伝わった。大人のあるべき姿というものを幹子さんは身につけたのだ。
彼女のスキルを大幅にアップさせる出来事が起こる。かねてから支援学級を持ちたいと考えていた幹子さんは、毎年のように希望を提出するも、なかなか採用されない。
8年目を迎えるころ、念願の支援学級の担任になることが叶った。校長先生との面談で、いきなり主任をして欲しいと言われる。
ベテランの先生のもとで学びたいと思っていたし、初めて支援学級の担任になる自分に、好きにしていいですよ、と言われ、おかしいなとは思ったがやっと念願が叶うのだから、まあいいかとあまり気にも留めなかった。
しかし、赴任してみると、周囲からみな「奥田さん、大丈夫?」と口々に心配される。何のことを言ってるのかよくわからなかったが、受け持ってみるとその言葉の意味がやっとわかった。
実は教育委員会でも有名な、クレーマー保護者がいたのだ。当初は別なベテランの先生が専属的にその保護者とお子さんについていた感じだったのが、その先生も辞めてしまい、幹子さんが受け持つことになった。
機嫌がよかったかと思うと急に豹変し、いったん認めていたことを覆されたりする。何かあればすぐに教育委員会へ連絡されるし、ときには自宅内でのトラブルなどにも呼び出されることもあった。
それは大変な7年間であったが、幹子さんは周辺がみんな避けてゆくその難しい役割を見事にこなし、校長からも絶大な信頼を得ることになった。
こうして特別支援コーディネーターとして頑張る彼女のもとには、発達障害と診断された子どもはもとより、診断はされていないが勉強についていけない、お友達とうまく付き合えないといった、いわゆるグレーゾーンの子たちも集まってきて、満員のような状態になってきた。
そこで幹子さんは保護者の方のお話を聞く機会が増えた。心を開いて親身に相談にのると、100%の母親が涙を流しながら胸の内を打ち明けてくれるのであった。そして母親が元気になると、子どもたちも元気になれるということが心に響いた。
お母さんのケアも含めて役に立ちたいと深く考えた時に、それを出来るのは教師じゃない、という結論に至ったのである。こうして次に彼女が身を置いたのは療育センターである。茶話会やペアレントトレーニングを通じて、保護者のケアにも携わるが、経営していくための体制とのジレンマで、自分が理想とするところを追い求めることなった。
そこでまた新たな出会いがターニングポイントとなる。日本コミュニケーション心理学協会代表の溝口氏の依頼で、協会の講師たちに発達障害についての講演をした。それを聞いた溝口氏は、これからの世の中に絶対必要なものだと閃いた。そして協会を立ち上げ、発達療育士という資格を認定し、広めていく活動を始めることとなったのだ。
2019年7月には、一般社団法人日本発達療育士協会を設立。こうして世間でようやく認知が広がりつつある発達障害についての療育、そして保護者のケアなどに携われる「発達療育士」の資格を広めるためのスタートラインに立った幹子さん。その願いはお母さんたちに「楽しく子育てをして欲しい」ということ。
日本の療育現場が欧米並みに大らかで、みんな違ってていいという本当の理解を得られる日まで、幹子さんは走り続ける。どんな困難も明るく乗り越えてきた彼女のパワーは、眩いばかりに道を切り拓く。誰もが生きやすい世の中を目指して。